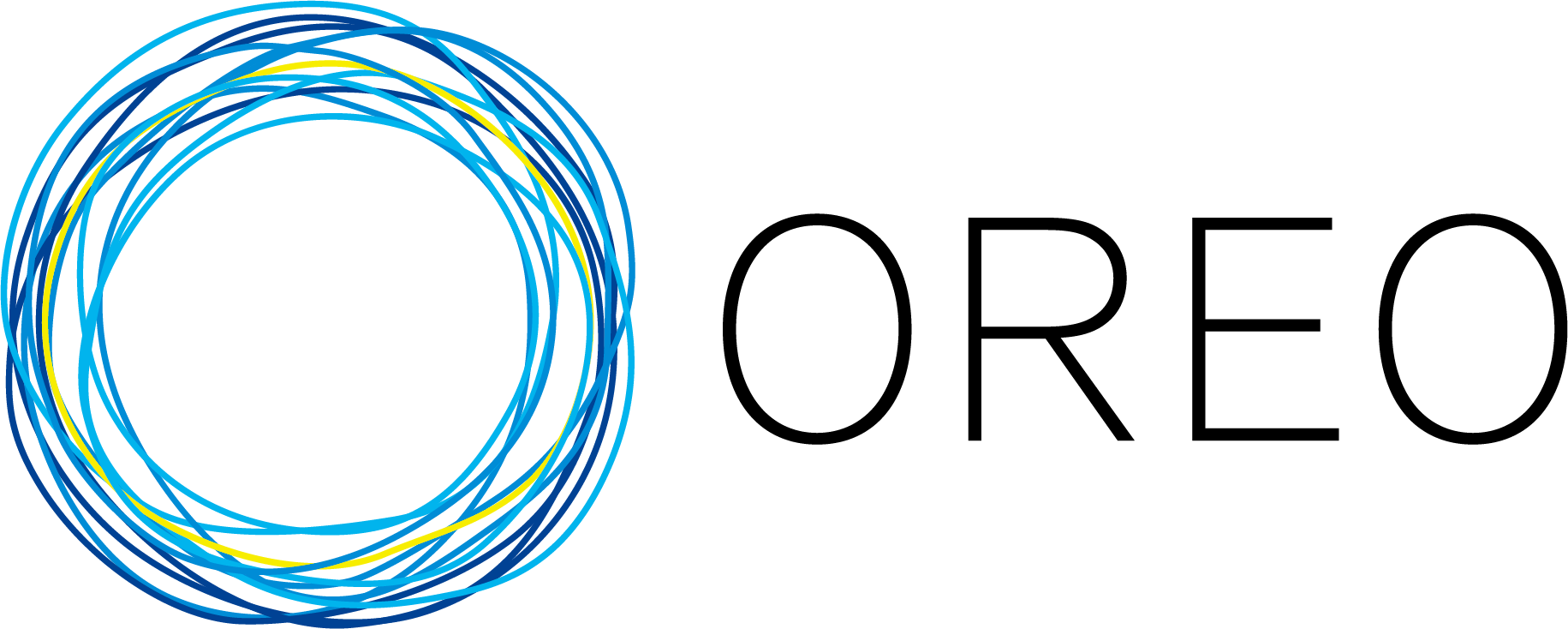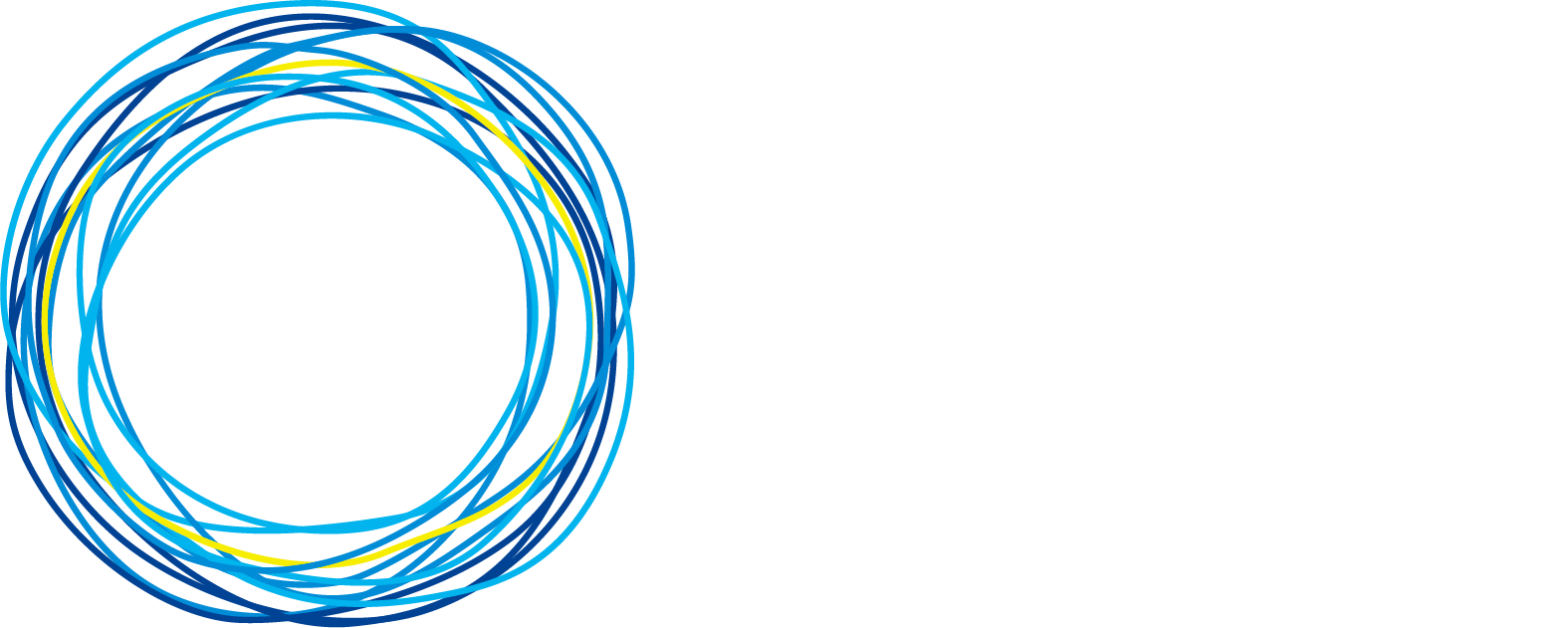「最近、だるい人が多い」そのとき講師ができること|ヨガレッスンで活かす夏バテ対策5選

「最近、生徒さんの表情がなんだか重い気がする」「レッスン中も疲れやすく、ポーズのキープができない」と、感じたことはありませんか?
夏の時期は、強い日差しと高温多湿、冷房の効いた室内との寒暖差など、私たちの自律神経にとって大きな負荷がかかりやすい季節です。
さらに、夜間の寝苦しさや食欲低下、水分・ミネラル不足といった要因も加わり「なんとなく調子が出ない」「とにかくだるい」といった状態に陥る方が少なくありません。
ヨガインストラクターとして、生徒の「微細な変化」に気づき、必要なサポートを届けることは、とても大切な役割ですよね。夏特有の「だるさ」に寄り添いながら、心身を調えるクラスをどう設計するか。
今回は、そんな視点で「夏バテ対策」として取り入れられる具体的なアプローチをご紹介します。


なぜ夏は「だるく」なるのか? 〜生理的・神経系の背景〜
夏の「だるさ」は、複数の要因が重なって起きている場合が少なくありません。医学的に明確な疾患ではなくとも、夏の暑さは、日常生活や運動パフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。
1. 自律神経の乱れ
暑さや強い紫外線は、交感神経を刺激しやすく、常に「興奮モード」に近い状態を生み出します。本来、交感神経と副交感神経は日内リズムの中でバランスを取っていますが、外的ストレスが続くことで、副交感神経への切り替えがうまく働かなくなり、疲労回復が進まなくなることが懸念されています。
2. 冷房による寒暖差ストレス
外気と室内との激しい温度差は、体温調節機能に負荷をかけ、影響を与えると考えられています。毎日続けることで心身が適応できなく可能性があるのです。
3. 胃腸機能の低下
胃腸機能は、副交感神経が優位であるときに活発になります。夏の暑さなどのストレスにより、交感神経が優位になり続けることで働きが鈍り、「食欲が出ない」「なんとなく重たい」といった症状を引き起こす可能性があります。
4. 睡眠の質の低下
夜間の気温が高いと、入眠障害や中途覚醒が増え、質の良い睡眠が取れない可能性があります。睡眠の質が低下すると、ホルモンバランスや自律神経の回復が妨げられ、慢性的な疲労感につながります。
5. 水分・ミネラル不足
発汗によって体内の水分・電解質が失われやすく、体への影響を与える可能性があります。そのため、水分とミネラルのこまめな補給は、夏の暑さ対策としてとても大切です。
ヨガインストラクターとして夏の暑さとの向き合い方 〜観察・配慮・設計〜
季節によって変化する生徒のコンディションに気づき、クラス全体の流れを調整できるのは、ヨガ講師ならではの重要なスキルです。とくに「だるさ」「疲れやすさ」「集中力の低下」といった夏特有のサインは、丁寧に観察することで早期にキャッチできます。
1. 観察:小さなサインを見逃さない
- 表情が硬い/まばたきが多い
- 呼吸が浅く、ポーズ中に揺れが目立つ
- 立位でふらつく、集中が続かない
こうした変化は、体調不良や自律神経の乱れが背景にあることも。とくに、夏場は寝不足や内臓疲労、脱水によって感覚が鈍っているケースもあるため、動きだけでなく「佇まい」や「沈黙」にも意識を向けておきましょう。
2. 配慮:励ましすぎず、緩める選択も
「がんばって動いてほしい」という気持ちが先行すると、かえって無理をさせてしまうことがあります。「今日は、今のままでいいよ」「呼吸に意識を向けていこう」など、体調に合わせた寄り添いの言葉がけが、安心感につながります。
また、元気そうに見える生徒ほど、無意識に無理をしている場合も。できる・できないではなく、「心地よさ」を判断基準にする声かけが、夏のクラスではとても大切です。
3. 設計:少ない動きでも深く効かせる
体力や集中力が落ちやすい夏は、アクティブなシークエンスばかりでは疲労感を助長することも。前半は呼吸を整え、副交感神経を高めるようなアーサナやフローから入り、後半に向けて循環・解放・リラクゼーションを意識した構成にすると、無理なく整える流れがつくれます。
ポイントは「動きの量」よりも「質と余白」。暑さで外向きに消耗しがちな意識を、静かに内側へ戻していく。その導きが、講師としての真価を発揮できるタイミングかもしれませんね。


ヨガクラスで活かす夏バテ対策5選
暑さによる「だるさ」に悩む生徒の多い夏こそ、シンプルで本質的なアプローチが役立ちます。ここでは、自律神経・循環・代謝・消化といった夏の不調に働きかける、ヨガクラスで取り入れやすい対策5つを紹介します。
① 呼吸法で内側から整える
呼吸が浅くなると、自律神経も乱れやすくなります。クラス冒頭や中盤で、「ナーディショーダナ(片鼻呼吸)」や「シータリー(冷却呼吸)」を取り入れることで、副交感神経を優位にし、心身の鎮静とリセットを促しましょう。
② ねじりと前屈で内臓と神経にアプローチ
夏は消化器の疲れが出やすい季節。内臓の働きを促す「ねじり系アーサナ」や、交感神経の高ぶりを静める「前屈ポーズ」を多めに組み込むと効果的です。特にツイストは、肋骨や横隔膜への刺激にもつながり、呼吸の深さを取り戻す助けにもなるでしょう。
③ リストラティブや軽めの逆転で回復モードへ
全力で動かすより「回復させる」ことが大切な日もあります。ブロックやボルスターを活用し、受け身で休める時間を用意してあげましょう。特に、脚を上げる逆転系(レッグアップなど)は、血流・リンパの還流を促し、下半身のむくみや冷えに効果的です。
④ 足元ケアで「冷え」&「むくみ」をほぐす
夏でも足元が冷えている生徒は多く、そこから自律神経の乱れや倦怠感につながることも。レッスン冒頭で、足指の解放や足裏ほぐしを取り入れるだけで、全身の感覚が目覚めていきましょう。
⑤ 香り・味・触覚など“五感”から整える
アロマの香り、ハーブティーの味、心地よいタッチなど、感覚刺激は神経系に穏やかな影響を与えます。とくに香りの力は即効性があり、ラベンダー・レモングラス・ミントなどは、リフレッシュと鎮静のバランスが取りやすいブレンドです。
ヨガで夏のケアを!だるさ”の奥にある声を聴こう
夏のヨガクラスでは、ただ「動く」だけでは届かない、繊細なケアが必要になることがあります。暑さや湿度、冷房による寒暖差、寝苦しさや食欲不振……。さまざまな要因が重なることで、生徒の心と体は「だるさ」というサインを発しています。
ヨガインストラクターにできるのは、その声なき声に気づき、寄り添うこと。
ときには「動かない選択」も含めて、心地よい時間を一緒につくっていくことです。
ぜひ、あなたらしい方法で取り入れながら、この季節ならではのクラスを育ててみてください。
----------------------------------
ヨガ資格RYT200・RYT500のオンラインと現地開催のハイブリット講座なら、自分のスケジュールに合わせて学べます。
OREO YOGA ACADEMYの講座なら、全国どこからでも自分のペースで学ぶことが可能です。
もちろん海外にお住まいの方でも参加できます。
一生つかえるヨガ資格であるRYT200・RYT500を自宅からオンラインで取得しませんか?
OREO YOGA ACADEMYでは、無料のオンライン説明会を随時行っております。お話を聞いてみたいという方は、「説明会を予約する」からご予約ください!


RYT200オンライン関連記事
RYT200はオンラインで今すぐ取らないと損!?2021年だけの特例措置?費用は?海外からでも取れる?
RYT200オンラインスクール選びに重要な4個のチェックリスト
【RYT200オンライン】テストは難しい?ちゃんと卒業できる?中間テスト、卒業テストの一部を公開!
フルタイムで働きながらでも2ヶ月でRYT200を取得!?オンラインだから実現した仕事と資格の両立。